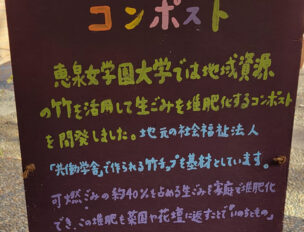和ろうそくは、つなぐ
著者:大西暢夫/出版社:アリス館
vol.08
日本の伝統的な灯具のひとつ、「和ろうそく」。どんな原料から、どうやって作られるのか。著者である大西暢夫さんの疑問から、和ろうそく作りをたどる旅は始まりました。
冒頭の舞台は愛知県岡崎市。夫婦で営む和ろうそく職人・松井さんの工房では、筒状にまいた和紙の上に“灯芯”(火を灯すひも状のもの。ここでは“灯芯草の髄”)を巻き付け、さらに灯芯がはずれないように真綿をからめる和ろうそくの芯作りや、ろうそくを太くするための “芯を取りつけた串に何度も手で蝋を塗って乾かす”作業が行われます。

その過程を見ながら、大西さんの中に生まれた新たな問いは「蝋は何でできているのか」。そんな関心を抱いて次に向かったのは、蝋の原料となるハゼの木の実の収穫地・長崎県島原市でした。
こんなふうに、次から次へとわき出る「何?」「なんだろう?」によって、和ろうそく作りの旅は、さまざまな伝統工芸の職人さんを訪ねる旅へと発展していきます。
伝統工芸品の原材料は、おもに自然の産物です。どの現場でも、捨てるものはほとんどありません。例えば、蝋を作るときに出た「蝋カス」は、福岡県広川町の藍染職人・森山さんのもとで、藍を発酵させる際に甕を温める火を持続させる燃料として使われます。藍染めの染液を作る際に使われた木の灰は、大分県日田市の職人・小袋さんによって、小鹿田焼の器に塗るうわぐすりに混ぜられます。

“ひとつの役割を終えたものが、つぎの職人の手によって、また生き返る。
そしてめぐりめぐって
ぼくたちが毎日使う器になってもどってくる。”(小鹿田焼き職人・小袋さん)
和ろうそくの作り方に始まり、原材料の蝋に焦点を移し、芯作り、真綿を生産する“お蚕様”へとたどった軌跡。本書は、人間が灯りを求めたときに、自然の営みに合わせたものづくりの歴史が育まれた事実と、人間と自然との共同で成り立った「循環」を教えてくれます。
記録としても見ごたえのある写真からは、職人魂が伝わり、ともに作業する家族と交わされる会話も聞こえてきそうなほど。また、どろどろした蝋の渦や、藍を炊く甕からゆらゆらと太く立ち上る湯気によって、五感は刺激を受けてフル稼働。まるでその場にいるような感覚におちいることでしょう。